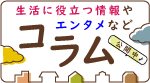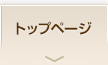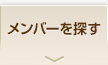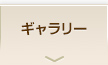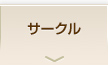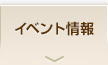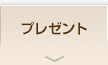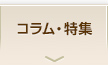メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
豊臣氏滅び毛利氏継続
2016年05月19日 
テーマ:テーマ無し
毛利氏(安芸国を拠点とした戦国大名の一族)
鎌倉時代末期に、現(広島県安芸)へ移り国人領主として成長
山名氏および大内氏の家臣として栄えた
戦国時代に、戦国大名への脱皮を遂げ、中国地方最大の勢力となる
関ヶ原の戦いで西軍の総大将となり、敗戦後周防国・長門国の2か国に減封された
約37万石の長州藩(萩藩)になり外様大名となる
明治維新を成就させる原動力となり、華族最高位の公爵を授爵
山口県を旅行し西国大名の知識不足痛感しました
毛利藩(ネットより引用)
毛利氏、家紋&家祖
家紋 長洲三星
家祖 大江季光
種別 武家華族(公爵)
毛利氏、家紋「一文字に三つ星」
「一文字に三つ星」を分解すると、一文字は「かたきなし」(無敵)の意味を持つ
三つ星は、軍神として信仰のあった将軍星(オリオンのベルト)を表している
全体的な形は、律令制における最高位を意味する「一品」(いっぽん)という文字を表している
毛利氏、鎌倉時代から室町時代
毛利氏としては季光を初代とするが、天穂日命を初代とするため、季光は39代とされている。
後醍醐天皇の討幕運動から元弘の乱が起こり、足利尊氏らが鎌倉幕府を滅亡させた
後醍醐天皇により開始された建武の新政からも距離を置いた為、鎌倉幕府与党として領土を没収された
南北朝時代には足利方に従い活躍している
毛利氏、戦国時代
安芸国の国人として土着した毛利氏
山名氏・大内氏という大勢力の守護に挟まれ去就に苦労することになる
大内氏と尼子氏とが安芸を巡って争い、安芸国内の国人同士の争いも頻発した
毛利元就(52代)は、その知略を尽くし、安芸国の小早川氏や吉川氏を乗っ取るなど勢力を拡大
元就は長男の毛利隆元(53代)に家督を譲ったのちも戦国大名として陣頭指揮を続け、大内氏との戦いで破った
吉川・小早川が安芸毛利当主家運営への参画、補佐することを条件に隆元が毛利家の家督を継いだ
毛利当主家を吉川家と小早川家でサポートする体制が成立し領国支配を磐石なものとした
毛利輝元(54代)が、尼子氏を滅ぼして、中国地方(安芸・周防・長門・備中・備後・因幡・伯耆・出雲・隠岐・石見)を領有した
織田信長の西国侵攻に対する抵抗勢力となるも、信長が急死したため領地を維持したまま織田方と和睦を結んだ
毛利氏、近世時代
豊臣秀吉の天下統一後、輝元は、広島城を築城し本拠を移り、五大老に就任
秀吉の死後は、石田三成と接近し、関ヶ原の戦いでは西軍の総大将に就く
吉川広家の、毛利氏は担ぎ上げられただけとの弁明により所領安堵の約定を得る
連判状に輝元の名があったことから、輝元は責任を問われ周防国・長門国(長州藩)に減封された
江戸時代末期、吉田松陰や高杉晋作、桂小五郎等の人材を輩出し明治維新を成就させた
毛利氏、明治時代以後戦前迄
大政奉還後、華族最高位の公爵を授爵された毛利氏は、身分的に徳川氏の風下に立つことはなくなる
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません