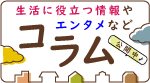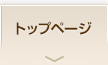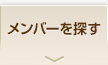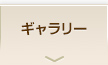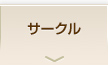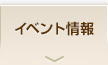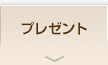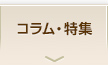メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
日本の仏教(「葬式仏教」構築)
2017年01月15日 
テーマ:テーマ無し
現在の「葬式仏教」の仕組みができあがる
江戸時代の本末制度と寺請制度は、寺院の権限を拡大させた
仏教界は固定化し、葬儀や法事などの儀礼が定着した
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください
出典、『宗教史(成美堂出版)』他引用&参照
☆本には、綺麗な絵画が記載されています
日本の仏教(『宗教史(成美堂出版)』、ネットより画像引用)
寺院を一括支配する本末制度制定の背景
江戸幕府成立以前は、都では僧兵の武力を背景とした南都北嶺(奈良と比叡山)の寺院の僧兵暴れる
江戸幕府成立以前は、地方では惣(農民らの地縁的な自治組織)を核に結集した一向宗や法華宗の一揆
江戸幕府成立以前は、これらの勢力が、政治・権力をおびやかした
織田信長、豊臣秀吉ら戦国大名に武力で鎮圧されて活動を沈静化した
徳川幕府政権は、本末制度制定
仏教勢力が力をもたないよう、寺院法度を制定し統制を図った
本末制度は、中世からあった本山―末寺体制を利用した
本山が傘下の寺院を格付けして末寺帳に記載し、幕府はこの末寺帳を提出させ上下関係を固定させた
結果、所属宗派を定めていなかった寺院も、いずれかの宗派の傘下に入った
本山は幕府に対しさまざまな義務を負つたが、末寺からの上納金を正当化でき人事権も掌握した
幕府統制下といっても、管理地の税徴収権、関係者の処罰権は本山が有し、強い自治権をもっていた
寺請負制度(徳川幕府政権ではお寺が戸籍係)
庶民の管理システムとして導入されたのが宗門改めと寺請の制度
宗門改めとはキリシタン禁令に対応したものです
☆家ごとに檀那寺とその宗派、構成員の人数などを記し、キリシタンでない保証を檀那寺が支配所に提出する
寺請制度とは、この檀那寺と檀家の関係を固定するもので、原則として地縁で選ばれた
☆檀家は、檀那寺を維持する責務を負い、怠ると檀那寺はその家の宗門改めを拒否できた
☆婚姻や奉公、旅行や引っ越しで移動する際にも、寺請証文という身分証明書を持ち歩かなければならなかった
檀那寺は、経済的負担を肩代わりしてもらう代わりに、檀家の葬儀や法事をとり行うようになった
一方庶民は行事や現世利益を寺に求めた
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません