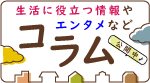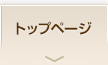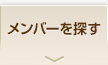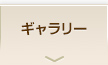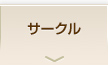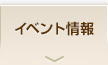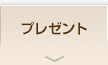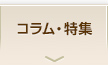メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
仏教(戒律)
2017年02月08日 
テーマ:テーマ無し
仏教徒が守るべき戒と教団の規則である律
仏教は、教団が拡大するにつれ修行者の心構えや教団内の規則が整えられていった
在家者の修行の心がけは戒、出家者の教団の規則は律とよばれ、2つ合わせて戒律という
}鑑真上人が、日本に伝えた具足戒と大乗菩薩戒
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください
出典、『宗教史(成美堂出版)』
☆本には、綺麗な絵画が記載されています
仏教(『宗教史(成美堂出版)』記事引用)
戒律(5戒と具足戒)
多くの信者を獲得した釈尊は、彼らに修行する際の心がけを教えあている
出家して共同生活を送る比丘、比丘尼が増えるに従い、教団内にはさまざまな問題も起こる
彼らはその都度、釈尊の判断を仰ぎ、教団の規則としていった
在家者の修行の心がけは戒、出家者の教団の規則は律とよばれ、2つ合わせて戒律という
律に違反した場合には、教団からの追放や謹慎などの罰則も設けられていた
在家信者の戒律(五戒)
1日限定で守る3つの節制を加えたものを八斎戒という
☆「歌舞をみたり、化粧や装身具で着飾ったりしない」
☆「心地よい寝具で寝ない」
☆「決まった時間以外に食事をしない」
これを守ることで、より出家修行者の生活に近づける
出家信者の戒律(具足戒)
比丘が250戒、比丘尼が348戒ある
釈尊の死後
仏教教団内部ではこの戒律の解釈などをめぐる論争が起きる
根本分裂にまでつながっていく
戒律をめぐる論争は続き、さまざまな戒律が体系化されていった
日本に伝わった具足戒と大乗菩薩戒
日本に戒律を伝えた律宗の鑑真は、具足戒に加え、大乗書薩戒といつ戒律も伝えている
大乗経典に由来するため梵網戒ともいわる
五戒を含む重要な十戒と、比較的軽い48の「十重四十八軽戒」からなる
大乗菩薩戒は、中国天台宗の祖が重視した
日本の天台宗にも影響を与え、最澄も比叡山大乗戒壇を設立するために奔走した
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません