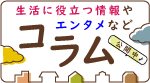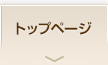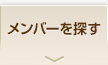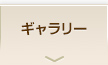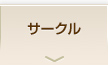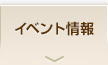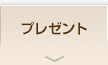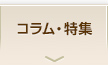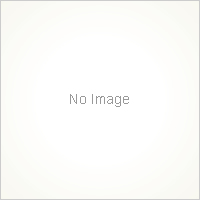メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2019年09 月( 3 )
- 2019年08 月( 12 )
- 2019年07 月( 29 )
- 2019年06 月( 28 )
- 2019年05 月( 25 )
- 2019年04 月( 28 )
- 2019年03 月( 30 )
- 2019年02 月( 28 )
- 2019年01 月( 26 )
- 2018年12 月( 25 )
- 2018年11 月( 29 )
- 2018年10 月( 31 )
- 2018年09 月( 29 )
- 2018年08 月( 7 )
- 2018年07 月( 31 )
- 2018年06 月( 24 )
- 2018年05 月( 22 )
- 2018年04 月( 28 )
- 2018年03 月( 28 )
- 2018年02 月( 28 )
- 2018年01 月( 31 )
- 2017年12 月( 24 )
- 2017年11 月( 30 )
- 2017年10 月( 31 )
- 2017年09 月( 28 )
- 2017年08 月( 13 )
- 2017年07 月( 26 )
- 2017年06 月( 29 )
- 2017年05 月( 25 )
- 2017年04 月( 28 )
- 2017年03 月( 39 )
- 2017年02 月( 28 )
- 2017年01 月( 27 )
- 2016年12 月( 28 )
- 2016年11 月( 28 )
- 2016年10 月( 27 )
- 2016年09 月( 27 )
- 2016年08 月( 17 )
- 2016年07 月( 26 )
- 2016年06 月( 30 )
- 2016年05 月( 23 )
- 2016年04 月( 30 )
- 2016年03 月( 31 )
- 2016年02 月( 29 )
- 2016年01 月( 27 )
- 2015年12 月( 27 )
- 2015年11 月( 30 )
- 2015年10 月( 25 )
- 2015年09 月( 28 )
- 2015年08 月( 21 )
- 2015年07 月( 23 )
- 2015年06 月( 31 )
- 2015年05 月( 25 )
- 2015年04 月( 29 )
- 2015年03 月( 28 )
- 2015年02 月( 28 )
- 2015年01 月( 25 )
- 2014年12 月( 26 )
- 2014年11 月( 28 )
- 2014年10 月( 40 )
- 2014年09 月( 30 )
- 2014年08 月( 13 )
- 2014年07 月( 31 )
- 2014年06 月( 27 )
- 2014年05 月( 21 )
- 2014年04 月( 30 )
- 2014年03 月( 6 )
日々是好日
生活と文化
2017年04月09日 
テーマ:テーマ無し
法事など
4/6日京都東山浄苑において毎年のように兄弟夫婦が集まり(姉の子供たち二名も含み)母の13回忌および父の法要を行いました。法要の後電車で有馬温泉に移動、姉の紹介で東急ハーベスト・クラブ(有馬六彩)に宿泊。翌日は有馬温泉観光。昼過ぎには大阪に移動、息子夫婦と孫二人と一緒に夕食を楽しみました。
昨日は朝から改めて京都に戻り、小雨降る京都の東山あたりの桜見物と謡蹟見学に出かけました。桜の満開時の清水寺は朝から交通は大渋滞です。朝早かったことと小雨が降っていたこともあり、多少は渋滞も緩和されていたのでしょうが、それでも多くの外国人観光客には驚かされました。
能「田村」の中入りは「地主権現の御前より、下るかとみえしが。下りはせで坂の上の田村堂の軒もるや・・・」で終わりますが、写真はその田村堂です。地主権現は今は地主神社と名前が変わり縁結びの神社です。能「田村」では自主権現の「地主の桜」も有名です。現在の地主の桜は植え替えられ若木でまだつぼみでした。
能「熊野」にあらわれる「愛宕の山もうちすぎぬ。六道の辻とかや。げに恐ろしやこの道は。冥途に通うなるものを。こころぼそ鳥辺山・・・」と謡われる六道はん(小野篁が開基といわれる珍皇寺)の謡跡(写真上)。昨日のブラタモリでも取材され紹介されていました。タモリさんの関心は専ら地形にあり、嵐山と清水寺当たりは同じ岩盤であったが、その間が地盤沈下で現在のような地形になったとのこと中心課題として取り上げられています。
六道はんの近くにある六波羅密寺は平家の公達たちが住まいしたところ。「平家物語」第四巻を現在聞いていますが当にその平家隆盛時代の中心地です。京都は平家の都落ちの際に火の海と化しますが、源氏の世には北条氏一門の者が就任し、尾張以西を掌握するため、鎌倉幕府の六波羅探題として機能しました。日々是好日。
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません