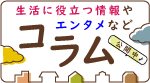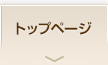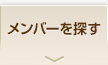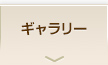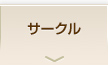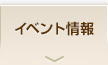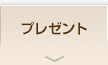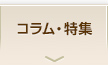メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
死者が「怨霊」で崇る日本人特有の考え
2018年12月19日 
テーマ:テーマ無し
平安時代2
武士の誕生
☆土地制度の崩壊とともに、貴族や僧侶による土地の私有化が始まる
*富裕な貴族や有力な寺が取得した土地は荘園と呼ばれた
*当時土地の正確な地籍図もなく、土地をめぐる争いは日常茶飯事
☆貴族たちは荘園を守るために用心棒のような男たちを雇った
*彼らは戦いに備えて武装していた
☆寺では下級僧侶たちが僧兵として自らを武装していた
☆国司として派遣された下級貴族の一部も土地を私物化した
*それを守るために自ら武装集団化した
*彼らは、戦闘の専門家となり、家業として受け継がれていく
*武士と呼ばれる存在となる
☆地方に有力な武士が誕生した
*棟梁と呼ばれる者を頂点とする一族を形成するようになる
☆関東を中心として勢力を広げた平氏
*平氏は、桓武天皇の流れを汲む皇族出身
☆摂津を河内を中心に勢力を広げた源氏
*源氏は、清和天皇の流れを汲む皇族出身
☆家格の高さから武士たちの尊敬を集め大きな勢力となる
藤原氏の台頭
☆財力を持った貴族が増え、藤原氏の財力はずば抜けていた
*藤原氏は飛鳥時代の中臣鎌足が始祖
*鎌足は「乙巳の変」で活躍したことで出世し藤原姓を与えられた
*藤原氏は、鎌足の子不比等の時代に大きな権力を得た
☆藤原氏(北家)は平安時代の中期から、 一族の娘を次々と天皇に嫁がせる
*天皇の外戚として力を振るう
*藤原氏の当主は摂政や関白として天皇の代わりに政治を執り行なった
☆菅原道真も藤原氏の策略により、九州の大宰府に流された
☆藤原氏が最も権勢を振るったのは道長の時代
*ライバルを次々に失脚させ天下を意のままにした
☆藤原道長家に、次々と不幸に見舞われる
*本人が身体の不調をきたす
*息子が死に、三人の娘もすべて死ぬ
☆藤原道長は、自分が政争で追い落とした者たちの崇りでと恐れた
「崇り」について
☆古の日本人は、非業の死を遂げた人は怨霊となって世の中や人に祟ると恐れた
*疫病が流行ったり、天災が続いたりすると崇りのせいだと考えた
*怨霊を鎮めるための祭りを行なったり、神社を作ったりした
☆怨霊を恐れる思想は、日本人の心の底に根強く残っていて、幕末の頃まで続いていた
☆明治維新以後、西洋風の合理主義が入り込んだ
*現代人は「崇り」や「怨霊」を非科学的なものとして排除するようになった
☆明治維新まで、人々の行ないは「祟り」や「怨霊」を恐れたゆえのものであったことが少なくない
平安時代の人々が恐れおののいた「菅原道真の崇り」
☆醍醐天皇により、大宰府に流された道真は、2年後に大宰府で亡くなる
☆「祟り」は、道真に死後に起きる
*道真を追い落とした藤原氏の主だった男たちが次々と急死
*その子供たちも次々と亡くなっていく
*道真を左遷に追いやった首謀者の藤原時平は、崇りに怯えながら狂い死
*皇太子までもが亡くなる
☆醍醐天皇は道真の怨霊を恐れた
*道真の左遷を取り消して名誉を回復させたが崇りは収まらなかった
*醍醐天皇は、朱雀天皇に譲位するが、その7日後に醍醐天皇は崩御する
☆朝廷は道真の怨霊を鎮めるために北野天満宮を作る
*道真の霊を祀って、ようやく祟りは収まった
☆その後も、人々は不遇の死を遂げた人物の崇りを恐れた
*彼らの怨霊を鎮めるために神社を作って、御霊を祀った
☆死者が崇るというこの考え方は日本人特有である
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『日本国紀』
死者が「怨霊」で崇る日本人特有の考え
(ネットより画像引用)
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません