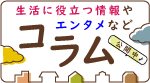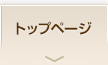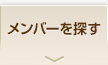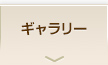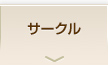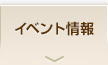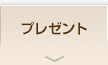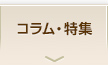メニュー
最新の記事
-

羽田を安全・安心の国際空港へ -

「蘆花恒春園震災トイレ」を防災マップに掲載しない官僚的な世田谷区 -

広島最大級の被爆建物・旧陸軍被服支廠の耐震化に29億円 広島県 -

沖縄県主催シンポジウム【 日米地位協定の改定に向けて−他国の地位協定との比較で見えた展望−】 -

沖縄県主催シンポジウム【 日米地位協定の改定に向けて−他国の地位協定との比較で見えた展望−】
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 25 )
- 2023年12 月( 53 )
- 2023年11 月( 44 )
- 2023年10 月( 50 )
- 2023年09 月( 41 )
- 2023年08 月( 58 )
- 2023年07 月( 41 )
- 2023年06 月( 44 )
- 2023年05 月( 31 )
- 2023年04 月( 39 )
- 2023年03 月( 53 )
- 2023年02 月( 41 )
- 2023年01 月( 46 )
- 2022年12 月( 70 )
- 2022年11 月( 48 )
- 2022年10 月( 58 )
- 2022年09 月( 43 )
- 2022年08 月( 71 )
- 2022年07 月( 55 )
- 2022年06 月( 54 )
- 2022年05 月( 50 )
- 2022年04 月( 63 )
- 2022年03 月( 50 )
- 2022年02 月( 33 )
- 2022年01 月( 45 )
- 2021年12 月( 46 )
- 2021年11 月( 44 )
- 2021年10 月( 52 )
- 2021年09 月( 41 )
- 2021年08 月( 47 )
- 2021年07 月( 45 )
- 2021年06 月( 50 )
- 2021年05 月( 58 )
- 2021年04 月( 63 )
- 2021年03 月( 57 )
- 2021年02 月( 51 )
- 2021年01 月( 39 )
- 2020年12 月( 27 )
- 2020年11 月( 23 )
- 2020年10 月( 27 )
- 2020年09 月( 20 )
- 2020年08 月( 65 )
- 2020年07 月( 59 )
- 2020年06 月( 51 )
- 2020年05 月( 61 )
- 2020年04 月( 59 )
- 2020年03 月( 70 )
- 2020年02 月( 65 )
- 2020年01 月( 58 )
- 2019年12 月( 59 )
- 2019年11 月( 49 )
- 2019年10 月( 42 )
- 2019年09 月( 56 )
- 2019年08 月( 60 )
- 2019年07 月( 36 )
- 2019年06 月( 28 )
- 2019年05 月( 41 )
- 2019年04 月( 49 )
- 2019年03 月( 57 )
- 2019年02 月( 50 )
- 2019年01 月( 62 )
- 2018年12 月( 44 )
- 2018年11 月( 28 )
- 2018年10 月( 48 )
- 2018年09 月( 44 )
- 2018年08 月( 48 )
- 2018年07 月( 21 )
- 2018年06 月( 27 )
- 2018年05 月( 36 )
- 2018年04 月( 48 )
- 2018年03 月( 49 )
- 2018年02 月( 44 )
- 2018年01 月( 39 )
- 2017年12 月( 35 )
- 2017年11 月( 15 )
- 2017年10 月( 33 )
- 2017年09 月( 38 )
- 2017年08 月( 39 )
- 2017年07 月( 21 )
- 2017年06 月( 25 )
- 2017年05 月( 35 )
- 2017年04 月( 46 )
- 2017年03 月( 52 )
- 2017年02 月( 36 )
- 2017年01 月( 33 )
- 2016年12 月( 36 )
- 2016年11 月( 15 )
- 2016年10 月( 35 )
- 2016年09 月( 36 )
- 2016年08 月( 27 )
- 2016年07 月( 43 )
- 2016年06 月( 34 )
- 2016年05 月( 23 )
- 2014年11 月( 8 )
- 2014年10 月( 10 )
- 2014年09 月( 13 )
- 2014年08 月( 5 )
- 2014年07 月( 22 )
- 2014年06 月( 25 )
- 2014年05 月( 24 )
- 2014年04 月( 12 )
- 2014年03 月( 21 )
- 2014年02 月( 23 )
- 2014年01 月( 17 )
- 2013年12 月( 26 )
- 2013年11 月( 22 )
- 2013年10 月( 13 )
- 2013年09 月( 17 )
- 2013年08 月( 22 )
- 2013年07 月( 18 )
- 2013年06 月( 4 )
- 2013年05 月( 4 )
- 2013年04 月( 5 )
- 2013年03 月( 4 )
- 2013年02 月( 6 )
- 2012年04 月( 2 )
- 2012年03 月( 12 )
- 2012年02 月( 27 )
- 2012年01 月( 12 )
- 2011年12 月( 10 )
- 2011年11 月( 11 )
- 2011年10 月( 15 )
- 2011年09 月( 14 )
- 2011年08 月( 10 )
- 2011年07 月( 13 )
- 2011年06 月( 18 )
- 2011年05 月( 14 )
- 2011年04 月( 6 )
- 2011年03 月( 18 )
- 2011年02 月( 14 )
- 2011年01 月( 7 )
- 2010年12 月( 9 )
- 2010年11 月( 3 )
- 2010年10 月( 4 )
- 2010年09 月( 6 )
- 2010年08 月( 5 )
- 2010年07 月( 6 )
- 2010年06 月( 2 )
- 2010年05 月( 6 )
- 2010年04 月( 8 )
- 2010年03 月( 7 )
- 2010年02 月( 11 )
- 2010年01 月( 5 )
葵から菊へ
「令和」の考案者中西進氏の論考「象徴天皇の祈り・ノットペリッシュ」
2019年04月07日 
テーマ:テーマ無し
Twitter「世に倦む日日」の管理人田中さんが論考『安倍晋三の本命元号を潰した皇室 - 皮肉が重なって誕生した「令和」 』をアップしました。
一部を抜粋します。
・・・・・・・・・・・・・・
2月以前の段階で中西進がその他大勢の考案者候補に含まれていたのは確かで、「令和」以外にも漢籍由来の万葉集出典案を幾つか提案していたのかもしれない。3月中旬という納期ギリギリの時点で本命案の委嘱依頼が来たとき、中西進は全てを察知し、あるいは両陛下の側近(三谷太一郎とか)から事情を聞き、知識人らしく、意を決して、皮肉を込めて反骨のカウンター作品を投擲したのではないか。「梅花の宴」の序文は王羲之の『蘭亭序』のエミュレーションであり、字句は張衡の『帰田賦』を踏んだオマージュの技巧だった。さらに『帰田賦』には時代背景があり、政治への痛烈な批判が表現されていた。
新元号は「令和」で決まった。日本の歴史に残る。中西進は壮絶な文化的事業をやり遂げたと言える。まさに東洋の知識人の理念と本分を千年単位の巨大な歴史的スケールで再現し、勇気と矜持をわれわれと後世の人々に示し、面目を躍如して先行する偉人の列に加わった。屈原や司馬遷の群像に連なった。これほど数奇な運命で策定された元号が他にあっただろうか。今度の元号は、初めての国書出典(表面の形式上だけだが)であると同時に、知識人が政権批判のブラックユーモアを意趣して制作し、それが皮肉な政治的展開で採用になった初めての元号である。二重三重の皮肉と偶然が重なり、瓢箪から駒の抱腹絶倒の歴史が作られた。そこには、文学と歴史を知らないイデオロギー偏執狂の独裁者がいて、間もなく退位する賢く思慮深い、勇敢で胆力のある老天皇がいた。今回の元号選定は明らかに政局であり、歴史に残る一つの重要な政治戦だった。野党と左翼リベラルの現役文化人は最初から白旗を上げて降参し、独裁者の大勝利で終わるかに見えたが、天皇(皇室・東宮)が粘り、粘り腰の末に同齢の老知識人と謀って逆転勝利を遂げた。
・・・・・・・・・・・・・・
「真面目に闘争したのは日刊ゲンダイだけだった。共産党も何もしなかった。」と言われていますが、共産党は、天皇制を認めていませんからあれこれ論評をしなかったのは当然だと思っています。
世田谷図書館から、日本クラブ編・角川書店刊「憲法についていま私が考えること」を借りてきました。
中西氏は明仁天皇美智子妃殿下の平和思考を高く評価されていることには、些かギャップもありますが。
・・・・・・・・・・・・・・
中西 進
象徴天皇の祈り・ノットペリッシュ
海に祈る--そうした皇帝像を思い浮かべると、これほど強烈で崇高な映像はそう多くはあるまい。それを三十年もの間続けられたのが、今上両陛下である。
いや、海ばかりではない。わが領土にまで敵の侵入を許してしまった沖縄戦では、危害をさえ危うくまのがれながらも、祈りを捧げつづけた。
とにかく日本は数年の間にアジア・太平洋の広域に、水損く屍、革むす屍を残した。その数三一〇〇〇〇〇人。一人が五人の家族を持っていたとして、優に当時の日本の人口の一割を超える人びとを悲嘆の底に陥れたことになる。
その者たちは「天皇陛下万歳」といって死ねと強制された。今上陛下はそのことを幼少年時に体験しているのであり、当の天皇を継いで皇位についたのだから、彼ら死者たちにどう対応するかが、今上陛下のお立場の原点になってしまった。
この原点の悲しみはいかばかりか。
そこでわたしには、長く考えてきたことがある。海に向かい山野に向かって頭を垂れる時、お心の中にあることばはどのようなことばか、という疑問である。必ずや無言のことばがおありだろう。それをぜひ知りたい。
そして次第にわかってきたことばがあった。
あの、名文をもって綴られた「日本国憲法」の前文に次のような一節がある。
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これによると、いかに「国民」が国家にとっても国政にとっても大切であるかが分かる。
さらにこの「国民」の重視が、一八六三年十一月十九日に行われた、アメリカの大統領リンカーンの、ゲティスパーグにおける戦没者への哀悼のことば「ゲティスパーグアドレス」の末尾に基づくことは、よく知られている。摘記すると末尾には、
人民の人民による人民のための政治(govrnment of the people for the people)
とある。
このアドレスはたった二分間で、しかも末尾はあわただしく書きかえられたものだという。このことばは、あえてつけ加えなければならないほどに重要なリンカーン政治のコンパクトな理念だったことがわかる。のちに殺害すらよび込む、殺害されて使命を全うすべき統治者の悲願だったのである。
もちろんこの悲願は南北戟争を避けることができず、多くの戦死者を出した。
その若者らを大規模な墓地に葬るに当っての慰撫のことばが、ゲティスパーグアドレスであった。
さてそこで、「日本国憲法」がリンカーンのゲティスパーグアドレスを理念として導入したのなら、それに伴って次のようなことも、「日本国憲法」に導入されたことになる。
リンカーンはいう。
われわれはここに、あなた方の死がむだに終わらないことを、高らかにわ宣言する(wehere highly resolve that these dead shail nothave dive in vain)
とくに今上陛下は世界の歴史に強い関心と知識をもたれ、一方、科学誌に学術論文も掲載される学者である。皇后陛下も読書量が豊かで、英語の著書もお持ちである。「日本国憲法」の中で自らがゲティスパーグアドレスによって枠組みされているからには、即位を機にアドレスを熟読なさっておられよう。
そう思い到った時、アドレスのある一節が強烈にわたしの胸に迫ってきた。
陛下の長年にわたる日々のお心に響きつづけたに違いない一節である。このお気持ちで、祈りを捧げつづけておられるのではないか、この一節の中の一語の発見によって、わたしの積年の疑問はいっきょに解決した。
すなわち、アドレスの末尾には、新国家が生まれれば、あなた方の死は「残酷な死ではなくなるだろう(shall not perish from the earth)」とあるではないか。
大変恐縮ながら両陛下は、海山の戦死者を労って、お心の中で。?not perish?と呟きつづけておられるのにちがいない。
のみならずperishという動詞は、とくに戦争と災害による死について用いられる。そこでもう一つ判ることは、両陛下が激戦地の他に、災害地へも度多く行かれていることだ。
戦没者戟没死と災害死、この二つを結ぶことばが、perishなのだ。
そこで次に、さらに大事なことが浮上する。?not perish?には条件があることだ。リンカーンは、自由(freedom)を実現する政府ができた暁には、南北戦争の戦死者がペリッシュといわれる死者ではなくなるのである。
リンカーンの自由の実現を日本では平和を実現する政府といいかえることになるだろう。
一九四六年以後、日本国憲法によって新しい日本が目ざしたのは、まさに自由で平和な国家だったからだ。
そこで重大な課題に気づく。もし平和を放棄すればどうなるのか。
それにこそ、いま日本人は気づかなくてはならない。
もう平和憲法は時代とそぐわないなどと勝手にきめつけて、これを放棄すれば、三一〇〇〇〇〇人はみな残酷な死者(perish)、無駄死にの死者(die in vain)として広漠たるアジア・太平洋の全域に横たわりつづけるままになるのだ。
それでいいのか。日本人はみな人間失格者となるのか。
陛下お一人にのみお任せしておこうというのか。
大地に横たわる無残な亡霊から戦死者を放い出すたった一つの手段が、平和日本の建設にもかかわらず一連の象徴天皇の行為を「政治的発言」だと批判する怒見があり、全国戦没者追悼式の「さきの大戦に対する深い反省」をネットで「反日」「自虐史観」と批判する書き込みもみられたという(中日新聞二〇一八年五月一日)。
わたしには大きな違和感がある。天皇の行為は「政治」でも「史観の表明」でもない。
ましてや自らが日本の象徴として行うことの中に「反日」という要素などどう存在するのか。この論理的矛盾は誰の目にも明らかであろう。
右の新聞記事の中には、陛下に近い方から会食の中で「陛下は絶対平和主義者みたいな人びとと同じか」といわれて「違うよ」と答えられたという記述もある。
お気持ちのもどかしさがよくわかる。
もどかしさとわたしが推測するのは、象徴天皇が「象徴」すべき日本とは何かを熟慮し、ゲティスパーグアドレスの論理を踏んで平和国家を実現し、ペリッシュから死者たちを救うことをあえて実行しておられるのに、それがイデオロギーでしか理解されないからだ。
ちなみにperishという単語は旧約聖書に一五六回(続編には五一回)も頻出する基本語である。神意に反した者の死を示す。正義を行なう者はpeishにならないことも、両陛 下はよく御存知だろう。
じっは一連の陛下の行為を「be を doにする」象徴天皇としての行為だろうと述べたことがある (藤原書店「機」二〇一七年九月〜二〇一八年三月)。それは「君臨すれども統治せず」という君主論と、近いかもしれない。しかもこれは、久しい伝統をもつ日本の王としてのあり方とも本質が近い。政治を「まつりごと」とよぶからだ。
わたしは象徴天皇を、これまた無礼な言だが、巨大な日本の良心だと心底から思っている。この良心の重要な中心に。?not perish?という祈りがある。この祈りをこそ日本人のすべてが、永遠に守りつづけていくべきである。
・・・・・・・・・・・・・・
(了)
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません