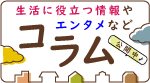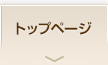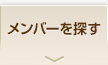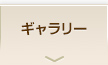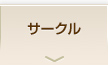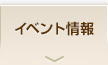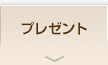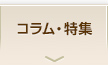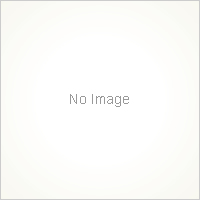メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2023年06 月( 10 )
- 2023年02 月( 9 )
- 2023年01 月( 2 )
- 2022年12 月( 11 )
- 2022年11 月( 11 )
- 2022年09 月( 1 )
- 2022年08 月( 8 )
- 2022年06 月( 1 )
- 2022年05 月( 5 )
- 2022年04 月( 9 )
- 2022年02 月( 5 )
- 2022年01 月( 28 )
- 2021年11 月( 1 )
- 2021年10 月( 12 )
- 2021年09 月( 13 )
- 2021年08 月( 18 )
- 2021年07 月( 30 )
- 2021年06 月( 45 )
- 2021年05 月( 11 )
- 2021年03 月( 1 )
- 2021年02 月( 38 )
- 2021年01 月( 8 )
- 2020年12 月( 13 )
- 2020年10 月( 20 )
- 2020年09 月( 20 )
- 2020年08 月( 22 )
- 2020年07 月( 14 )
- 2020年06 月( 28 )
- 2020年05 月( 13 )
- 2020年04 月( 39 )
- 2020年03 月( 41 )
- 2020年02 月( 42 )
- 2020年01 月( 28 )
- 2019年12 月( 1 )
- 2019年11 月( 4 )
- 2019年10 月( 5 )
- 2019年09 月( 4 )
- 2019年08 月( 11 )
- 2019年07 月( 35 )
- 2019年06 月( 19 )
- 2019年05 月( 26 )
- 2019年04 月( 17 )
- 2019年03 月( 17 )
- 2019年02 月( 6 )
- 2019年01 月( 40 )
- 2018年12 月( 13 )
- 2018年11 月( 19 )
- 2018年10 月( 12 )
- 2018年09 月( 16 )
- 2018年08 月( 43 )
- 2018年07 月( 39 )
- 2018年06 月( 38 )
- 2018年05 月( 34 )
- 2018年04 月( 34 )
- 2018年03 月( 36 )
- 2018年02 月( 15 )
- 2018年01 月( 6 )
- 2017年12 月( 11 )
- 2017年11 月( 6 )
- 2017年10 月( 16 )
- 2017年09 月( 15 )
- 2017年08 月( 1 )
- 2017年05 月( 6 )
- 2017年04 月( 9 )
- 2017年03 月( 17 )
- 2017年02 月( 9 )
- 2017年01 月( 40 )
- 2016年12 月( 7 )
- 2016年11 月( 1 )
- 2016年10 月( 7 )
- 2016年09 月( 11 )
- 2016年08 月( 1 )
- 2016年07 月( 8 )
- 2016年06 月( 12 )
- 2016年05 月( 10 )
- 2016年04 月( 4 )
- 2016年03 月( 14 )
- 2016年02 月( 40 )
- 2016年01 月( 33 )
- 2015年12 月( 12 )
- 2015年11 月( 29 )
- 2015年10 月( 11 )
- 2015年09 月( 7 )
- 2015年08 月( 23 )
- 2015年07 月( 14 )
- 2015年06 月( 30 )
- 2015年05 月( 45 )
- 2015年04 月( 39 )
- 2015年03 月( 15 )
- 2015年02 月( 20 )
- 2015年01 月( 49 )
- 2014年12 月( 60 )
- 2014年11 月( 33 )
- 2014年10 月( 11 )
- 2014年09 月( 22 )
- 2014年08 月( 35 )
- 2014年07 月( 67 )
- 2014年06 月( 42 )
- 2014年05 月( 38 )
- 2014年04 月( 62 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 43 )
- 2014年01 月( 51 )
- 2013年12 月( 32 )
- 2013年11 月( 26 )
- 2013年10 月( 11 )
- 2013年09 月( 36 )
- 2013年08 月( 79 )
- 2013年07 月( 72 )
- 2013年06 月( 68 )
- 2013年05 月( 57 )
- 2013年04 月( 59 )
- 2013年03 月( 46 )
- 2013年02 月( 73 )
- 2013年01 月( 114 )
- 2012年12 月( 96 )
- 2012年11 月( 21 )
- 2012年10 月( 55 )
- 2012年09 月( 34 )
- 2012年08 月( 34 )
- 2012年07 月( 67 )
- 2012年06 月( 90 )
- 2012年05 月( 97 )
- 2012年04 月( 108 )
- 2012年03 月( 104 )
- 2012年02 月( 120 )
- 2012年01 月( 93 )
- 2011年12 月( 74 )
- 2011年11 月( 68 )
- 2011年10 月( 77 )
- 2011年09 月( 80 )
- 2011年08 月( 62 )
- 2011年07 月( 79 )
- 2011年06 月( 87 )
- 2011年05 月( 91 )
- 2011年04 月( 70 )
- 2011年03 月( 64 )
- 2011年02 月( 69 )
- 2011年01 月( 135 )
- 2010年12 月( 104 )
- 2010年11 月( 86 )
- 2010年10 月( 57 )
- 2010年09 月( 52 )
- 2010年08 月( 98 )
- 2010年07 月( 73 )
- 2010年06 月( 58 )
- 2010年05 月( 32 )
- 2010年04 月( 52 )
平成の虚無僧一路の日記
伊豆半島一周の旅
2019年05月04日 
テーマ:テーマ無し
令和元年最初の虚無僧の旅は伊豆半島一周。
最初に向かったのは修善寺の南、大平の旭瀧。
真東を向いており、朝日を浴びて輝くところから旭瀧。
(地元では「あさひだる」と呼ぶそうな)
全長105メートル。六段に落ちるので、各段それぞれに水の音が異なる。
瀧の麓に「功徳山瀧源寺(ろうげんじ)」という虚無僧寺があった。
瀧の中腹の傍らには、歴代住持(看主)の墓と思われる6基の無縫塔(卵塔)がある。
虚無僧本曲の「瀧落ちの曲」は、ここの虚無僧によって作られ伝承されたとされる。
瀧源寺は明治4年に普化宗廃宗により廃寺となり、寺の本尊であった木彫十一面観音菩薩立像と
木彫不動明王坐像の二体は近くの金龍院という寺に移され安置されている。
?
この金龍院は、北条早雲と葛山氏の娘との間に生まれた北条幻庵の菩提寺。
玄庵とその母、姉、妹の位牌がある。玄庵は幼い頃京都で育てられており、
茶や連歌に通じた文化人で一節切(ひとよぎり)の名手だった。
その影響で小田原北条家の家臣の多くが尺八を吹いた。
幻庵は90歳まで長生き(戦国武将の中で最長)。小田原北条家5代に
わたって生き、長老として君臨し、天正18年に小田原北条家が秀吉に攻められて
滅びる、その前年まで生きた。
?
関東の虚無僧寺の多くが、北条家の浪人によって作られたものと推察される。
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません