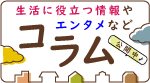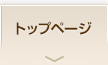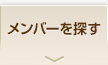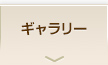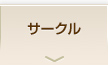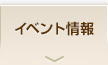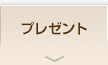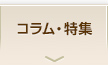メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
昔の日本のしきたり(歳・民間療法科学的なのと迷信)
2019年11月05日 
テーマ:テーマ無し
昔の日本のしきたり
☆昔はお餅を食べて歳をとった
(お正月は家族と一緒に歳をとる「数え歳」)
☆風邪をひいた人の首に焼いたねぎを巻くとよい
(民間療法は知識と迷信、そして生活の知恵)
昔はお餅を食べて歳をとった
☆お年玉とは、「年の魂」を意味する
☆「年の魂」
*お米には霊力が宿り、お米の霊力への信仰があった
*正月のお餅は、そのお米の霊力の象徴です
☆お餅を食べることで、歳をとる
*昔は正月で歳をとる、「数え歳」でした
☆お年玉とは、正月に食べるお餅のこと
☆正月には
*家族は主人から着物や身の周りの物を新調してもらう
*お小遣いももらうので、お参りに行って露店などで買い食いもできた
*昔は、買い食いという言葉自体悪い意味でしたが、正月だから許されていた
風邪をひいた人の首に焼いたねぎを巻くとよい
☆ねぎは食用や薬用のために古くから栽培されていた
*高熱や疼痛、むくみ、また虫などによる咬傷の洗浄にも使われていた
*首に焼きねぎを巻く風邪の療法もあながち無視できない
☆言い伝えには、呪術的なものもある
*科学的な実証が難しいもので、迷信といわれることも多い
*心にまつわる病は、薬草などの効力の及ばない場合が多い
*そこで呪術的な方法を用いることも行なわれてきた
☆”カラスが鳴いたら人が死ぬ”という迷信
*カラスの鳴き声を聞き分ける能力のある人が言い出したことでしよう
*鳴き声の聞き分けの部分が飛んで、”カラスが鳴くと人が死ぬ”と変化した
*”カラスは不吉だ”となり、そうなると迷信になる
☆「類感呪術」や「感染呪術」というタイプもある
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『なるほど!民俗学』
昔の日本のしきたり(歳・民間療法科学的なのと迷信)
(『なるほど!民俗学』記事より画像引用)
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません