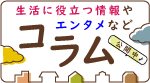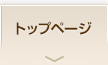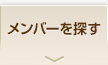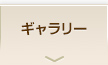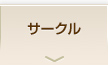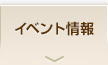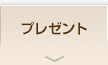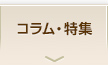メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
がん免疫療法2(免疫抑制機構の応用)
2020年04月19日 
テーマ:テーマ無し
免疫抑制機構を逆手にとるがん細胞
☆一部のがん細胞は、がん免疫(がん細胞を排除する)を抑制する
☆獲得免疫機構には、免疫反応の暴走を食い止めるためのしくみがある
☆免疫反応はでは、病原体など非自已の侵入を感知する
*非自己の病原体を排除するが、自己と非自己の判別は完全でない
*理由として、リンパ球が自己の細胞を攻撃する危険をはらんでいるから
*免疫系の暴走にブレーキをかける細胞や分子が存在する
☆結果として、免疫抑制機構が働かなくなる
*自己を攻撃するリンパ球の数が増えて、自己の体成分を破壊する
*関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群などの病気
☆がん細胞は、「がん免疫」を無効化させていることがわかってきた
獲得免疫を抑制する機構
☆制御性T細胞
*Tリンパ球の一種で、免疫反応にブレーキをかける役割を持っている
*この細胞はIL‐10などの抑制性サイトカインを作る
*ヘルパーTリンパ球が、抗原提示細胞と相互作用するのを邪魔する
*主にTリンパ球の働きにブレーキをかけ、Tリンパ球の働きが弱くなる
*抗体を作るBリンパ球は、Tリンパ球からのヘルプが必要である
*結果、Bリンパ球の働きが止まり、免疫反応全体がおさまる
☆がんができると、制御性T細胞の数が増え、がんに対する免疫を抑制する
補助刺激分子と免疫チェックポイント分子
☆Tリンパ球が、樹状細胞からの抗原提示を受けて増殖する際
☆Tリンパ球上の抗原レセプター
*MHC分子を介し提示される抗原ペプチドと結合する
(CD4又はCD8分子が樹状細胞上のMHC分子と結合することが必要)
☆Tリンパ球が抗原提示細胞と結合
*Tリンパ球内に「補助シグナル」という特殊な刺激が入ることが必要
*「補助シグナル」多くの種類があり、細胞膜の上に存在するタンパク質である
☆抗原を提示する樹状細胞
*未熟なうちは補助刺激分子をあまり持っていないが、刺激を受けて成熟すると
*2種類の補助刺激分子を細胞膜上に多数持つ
☆Tリンパ球の膜上に、分子に結合できるCD28という補助刺激分子が存在してる
*Tリンパ球が抗原を提示する樹状細胞と出会うと
*樹状細胞からの「MHC+抗原」提示によるシグナルが入る
*Tリンパ球上のCD28が樹状細胞上の2種類に結合する
*Tリンパ球内に補助シグナルが入り、Tリンパ球が増殖する
☆抗原によるシグナル(シグナル1)と補助刺激分子によるシグナル(シグナル2)
☆両方のシグナルが入ったときに、Tリンパ球の増殖が始まる
☆シグナル2が入らないと、Tリンパ球は増殖できず
アナジー(無反応)とは
☆抗原に再び出会っても反応しないようになる
☆CD28という補助刺激分子は、Tリンパ球の反応性を強める役割を持っている
☆補助刺激分子(CTLA−4やPD−1等)は、Tリンパ球の反応を抑制する
☆細胞膜上に存在し、相手の分子と結合し、Tリンパ球に「負のシグナル」を送る
☆CTLAー4、PDー1は、がん患者のTリンパ球で発現が増えている
☆がんそのものが免疫にブレーキをかける
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『免疫力を強くする』
がん免疫療法2(免疫抑制機構の応用)
(『免疫力を強くする』記事より画像)
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません