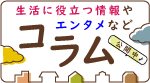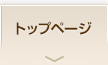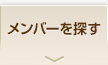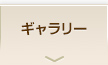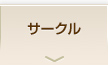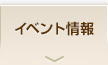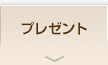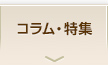メニュー
最新の記事
-

「ライドシエア」「犬の?」「飛行機内で性交」 -

「インフレと株価」「コストプッシュ型」 -

「地下アイドル」「メン地下」「推し活」 -

「道徳の帳尻合わせ」「シロクマ効果」「カラー/ジェンダーブラインド」 -

「宿題の外注」「女性によるDV」「いじめ」
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年01 月( 68 )
- 2023年12 月( 124 )
- 2023年11 月( 107 )
- 2023年10 月( 122 )
- 2023年09 月( 111 )
- 2023年08 月( 133 )
- 2023年07 月( 125 )
- 2023年06 月( 103 )
- 2023年05 月( 109 )
- 2023年04 月( 106 )
- 2023年03 月( 95 )
- 2023年02 月( 91 )
- 2023年01 月( 107 )
- 2022年12 月( 105 )
- 2022年11 月( 94 )
- 2022年10 月( 104 )
- 2022年09 月( 99 )
- 2022年08 月( 108 )
- 2022年07 月( 114 )
- 2022年06 月( 98 )
- 2022年05 月( 115 )
- 2022年04 月( 101 )
- 2022年03 月( 112 )
- 2022年02 月( 98 )
- 2022年01 月( 114 )
- 2021年12 月( 110 )
- 2021年11 月( 116 )
- 2021年10 月( 110 )
- 2021年09 月( 105 )
- 2021年08 月( 121 )
- 2021年07 月( 111 )
- 2021年06 月( 105 )
- 2021年05 月( 103 )
- 2021年04 月( 104 )
- 2021年03 月( 121 )
- 2021年02 月( 120 )
- 2021年01 月( 122 )
- 2020年12 月( 99 )
- 2020年11 月( 103 )
- 2020年10 月( 119 )
- 2020年09 月( 122 )
- 2020年08 月( 117 )
- 2020年07 月( 111 )
- 2020年06 月( 116 )
- 2020年05 月( 132 )
- 2020年04 月( 101 )
- 2020年03 月( 108 )
- 2020年02 月( 100 )
- 2020年01 月( 100 )
- 2019年12 月( 93 )
- 2019年11 月( 105 )
- 2019年10 月( 98 )
- 2019年09 月( 117 )
- 2019年08 月( 112 )
- 2019年07 月( 123 )
- 2019年06 月( 94 )
- 2019年05 月( 92 )
- 2019年04 月( 86 )
- 2019年03 月( 106 )
- 2019年02 月( 84 )
- 2019年01 月( 85 )
- 2018年12 月( 70 )
- 2018年11 月( 83 )
- 2018年10 月( 106 )
- 2018年09 月( 100 )
- 2018年08 月( 114 )
- 2018年07 月( 113 )
- 2018年06 月( 102 )
- 2018年05 月( 111 )
- 2018年04 月( 98 )
- 2018年03 月( 93 )
- 2018年02 月( 96 )
- 2018年01 月( 99 )
- 2017年12 月( 88 )
- 2017年11 月( 99 )
- 2017年10 月( 94 )
- 2017年09 月( 95 )
- 2017年08 月( 95 )
- 2017年07 月( 101 )
- 2017年06 月( 72 )
- 2017年05 月( 97 )
- 2017年04 月( 90 )
- 2017年03 月( 97 )
- 2017年02 月( 91 )
- 2017年01 月( 81 )
- 2016年12 月( 100 )
- 2016年11 月( 96 )
- 2016年10 月( 100 )
- 2016年09 月( 103 )
- 2016年08 月( 103 )
- 2016年07 月( 89 )
- 2016年06 月( 93 )
- 2016年05 月( 82 )
- 2016年04 月( 85 )
- 2016年03 月( 81 )
- 2016年02 月( 81 )
- 2016年01 月( 77 )
- 2015年12 月( 91 )
- 2015年11 月( 89 )
- 2015年10 月( 94 )
- 2015年09 月( 80 )
- 2015年08 月( 89 )
- 2015年07 月( 94 )
- 2015年06 月( 80 )
- 2015年05 月( 83 )
- 2015年04 月( 68 )
- 2015年03 月( 78 )
- 2015年02 月( 77 )
- 2015年01 月( 68 )
- 2014年12 月( 78 )
- 2014年11 月( 80 )
- 2014年10 月( 83 )
- 2014年09 月( 74 )
- 2014年08 月( 61 )
- 2014年07 月( 72 )
- 2014年06 月( 77 )
- 2014年05 月( 61 )
- 2014年04 月( 55 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 48 )
- 2014年01 月( 50 )
- 2013年12 月( 50 )
- 2013年11 月( 58 )
- 2013年10 月( 55 )
- 2013年09 月( 51 )
- 2013年08 月( 46 )
- 2013年07 月( 54 )
- 2013年06 月( 71 )
- 2013年05 月( 39 )
- 2013年04 月( 41 )
- 2013年03 月( 15 )
慶喜
自分で人生を作り出すということ(1)
2020年06月18日 
テーマ:テーマ無し
自分で人生を作り出すということ(1)
いかに死に備えればいいか
☆死ぬのが怖いという感覚は誰にでもある
☆年齢を重ねれば、死をイメージする時間が増えてくる
☆自分なりの「死生観」をもてば
*死をただ恐れるのではなく、受け入れられるようになる
☆境地に行き着くためには何をやるべきかと考える必要がある
☆死生観を培う、死生観を鍛える重要性
*先人たちは、やり方を変えながらこの作業を続けてきた
☆人間が生み出したもののひとつが「来世」
*来世があるなら、現在の生が失われても次があると安心できる
*来世の″発明″こそ、人類の不安を小さくした非常に大きいこと
☆いい人生を送れていると思っている人
*来世も同じように生きていきたいと楽しみに出来る
☆人生がつらいと思っている人
*来世に望みをかけられる
☆死の不安をやわらげる「来世」の考えは有効に作用している
*死を”妄想”に近いものだと考えることも可能
*「死は存在しない」と理解もできる
☆死後の世界へ行って戻ってきた人はいない
*生が終わったあとに何があるかは誰にもわからない
☆経験できないものの影に怯えて不安になる
*幻想に支配されているのと同じ
*そんな呪縛からは解き放たれておくべき
☆『来世』は、死の不安を打ち消すための装置(=宗教)である
孔子の教えと「ING」の力
☆『論語』で死生観にヒントを示す言葉
『敢えて死を問う。曰く
未まだ生を知らず。焉(いずく)んぞ死を知らん』
*孔子の回答は、死の本質を捉えたもの
*生きているのがどういうことかもまだわかっていないのに
どうして死がどんなものなのかわかるはずがあろうか
死が存在するかどうかもわからないではないか
☆孔子は、死後の世界については積極的に論じようとはしてない
☆孔子の思想に基づく儒教は、宗教ではなく道徳だといわれる所以
*孔子も人の死を悲しんでいる教えもある
☆『論語』で注目したい言葉
『子曰く
朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり』
*朝に「正しく生きる道」を聞けたなら
*その日の晩に死んでもかまわない
*孔子は死を恐れているわけではなく
*正しい道を知ることを何より優先していた
☆何かしらの目指すところがあり、かなえられたなら
死んでもいいという熱意をもてたならいい
☆たとえ達成できなくても、目指して進んでいく姿勢が大切
☆孔子の場合は、答えといえるものが見つけにくかったはず
最終到達地点といえるものはない
☆永遠に探し続けることを前提にしたINGだった
(敬称略)
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『極上の死生観』
自分で人生を作り出すということ(1)
(ネットより画像引用)
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません