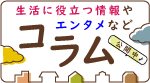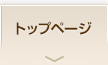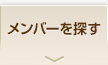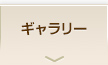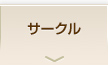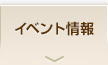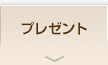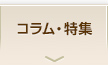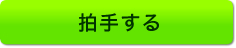メニュー
筆さんぽ
はじめの一行
2024年03月07日 
テーマ:筆さんぽ
どんな文章であっても、ぼくは、はじめの一行に注目いしたい。
「指先から煙草が落ちたのは、月曜の夕方だった」(向田邦子『思い出トランプ』「かわうそ」/新潮社)
若いころ、友人が貸してくれた一冊の本を開き、「はじめの一行」を目にしたとき、ちいさな衝撃のようなものを受けた。
このころは、広告文をつくる仕事(コピーライター)をしていた。広告コピーの世界では、「文章の一行目は、二行目を読みたくなるように書く」ことが基本であった。あたりまえのことだが、
斬新なメディア論を展開したマクルーハン(評論家の竹村健一さんが日本に紹介した)は「広告は洗濯機を売るのではなく、『洗濯機のある生活』を売るのである」といっていたから、やはり二行目、三行目を読ませたい。
向田邦子の、この本を読んだとき、文学の世界(『思い出トランプ』は1980年直木賞受賞)でも、「文章の一行目は、二行目を読みたくなるように書く」のではないかと思った。「かわうそ」は、気立てもよく、明朗で、かわいい女房のなかにある「もうひとりの女」に気づいてゆく夫の心象が主題となっているが、「はじめの一行」がこの心象を暗示しているように思えた。
エッセイや小説を書こうとしたとき、ぼくは「はじめの一行」にこだわりたい。
作家の河野多恵子さんはこういう。
「文学作品としての小説の場合、そういう書き方(途中や最後から書くなど)から、よい作品は決して生まれない。文学作品の小説は生き物だからである。人形制作のように、マスクやボディや手足をばらばらに拵えておいて、繋ぎ合わせるというわけにはゆかない。嬰児が次第に育ってゆくように、全身的な育ち方をするのである」(『小説の秘密をめぐる十二章』/文春文庫)。
河野多恵子さんが「途中から書いたら、よい作品は生まれない」と言い切っているからだろうか、ずばり『小説の一行目』(小説の一行目研究会/しょういん)という本を図書館で見つけた。芥川賞、直木賞の一行目(文章のひとくだり)だけが掲載してある。全頁に目を通すと、心うならせる一行が目に飛び込んでくる。(その一部を紹介・順不同)
寺石は傾斜のゆるい坂道をのぼっていた。
(立原正秋『白い罌粟』)
陸に上がった後も海のことがいつまでも忘れられない。
(辻仁成『海峡の光』)
朝、電話で隆志が、私のでてくる夢をみたという。
(江國香織『号泣する準備はできていた』)
飛行機の音ではなかった。
(村上龍『限りなく透明に近いブルー』)
星ひとつ見えぬ冬の夜の闇もこれほど黒くはあるまい。
(海音寺潮五郎『天正女合戦』)
小さな花をつけた二本の草。
(丸谷才一『年の残り』)
竜哉が強く英子に魅かれたのは、彼が拳闘に魅かれる気持と同じようなものがあった。
(石原慎太郎『太陽の季節』)
一九三〇年三月八日。
(石川達三『蒼氓』)
その部屋にいるのは、三人だけだった。
(五木寛『蒼ざめた馬を見よ』)
ジョン万次郎の生れ故郷は、土佐の国幡多郡中の浜という漁村である。
(井伏鱒二『ジョン萬次郎漂流記』)
私はその頃、アルバイトの帰りなど、よく古本屋に寄った。
(柴田翔『されどわれらが日々』)
からだが大儀になったせいか、達子は次の駅で降りる人を見分けるのがうまくなった。
(向田邦子『思い出トランプ』「犬小屋」)
コメントをするにはログインが必要です
同感です
私もです。
ほんの一呼吸、或いは二呼吸で読める一行目を本文への導入として重視しています。
ふしぎな客だった。
(五木寛之『晴れた日には鏡をわすれて』)
この本は今まで一番短い一行目でした。
2024/03/07 09:50:13